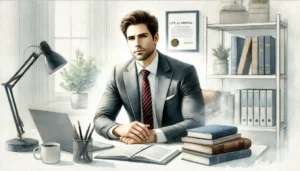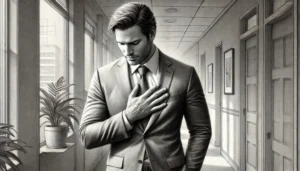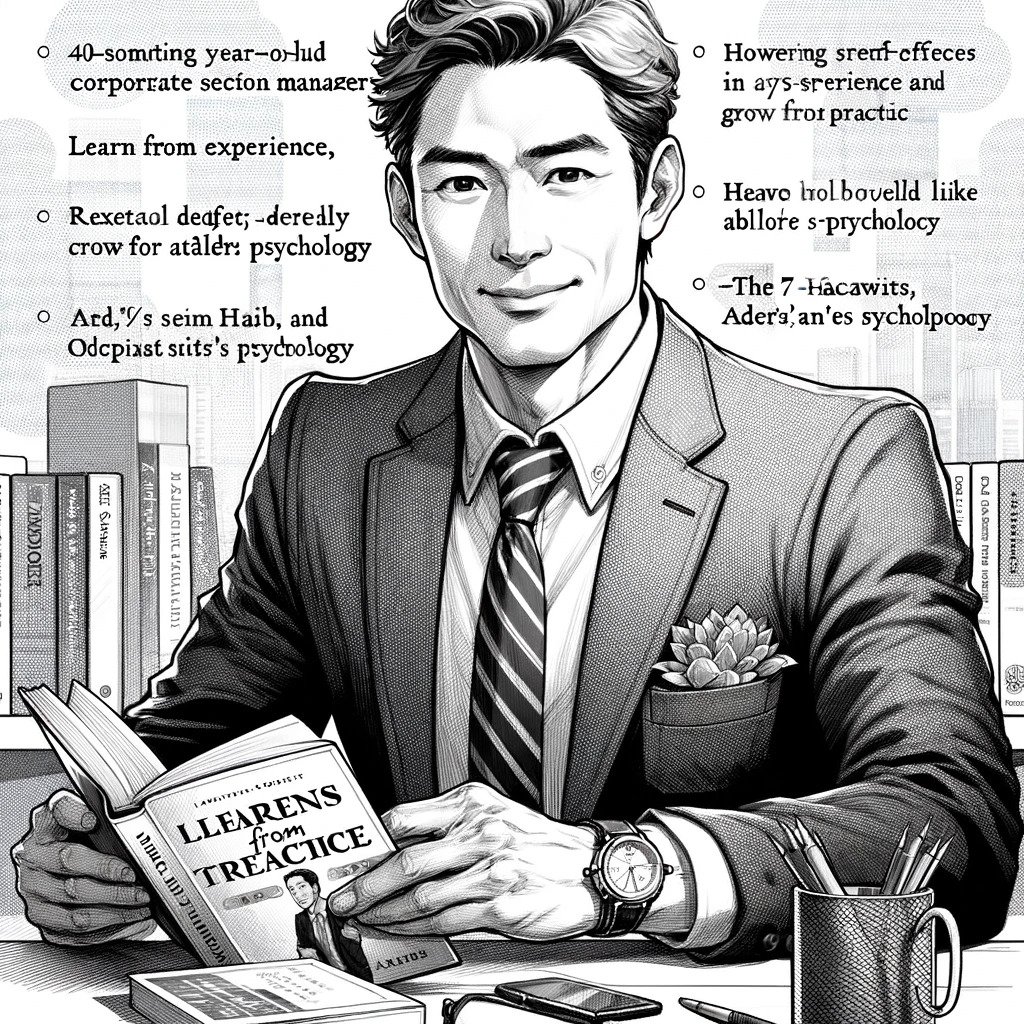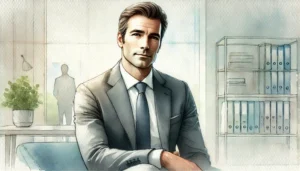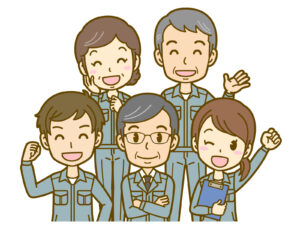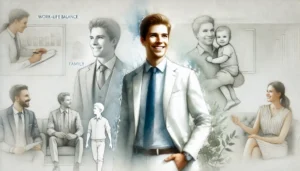はじめに
「自分はリーダーに向いていない」
そう思ったことは、何度もありました。
声が大きいわけでもなく、コミュニケーションが得意というわけでもない。
でも、40代後半となった今、課長という立場で現場に立ち続けながら、
私は“マネジメントの主体者”でありたいと強く思っています。
チームの力を引き出し、協働の中からシナジーを生み、成果を最大化する。
そのために自分の強みも弱みも受け入れ、
傾聴し、俯瞰し、ときには自らが先頭に立つ。
マネジメントは、任されてやるものではなく、自らの意思で引き受ける“仕事”であり“覚悟”だと、私は信じています。
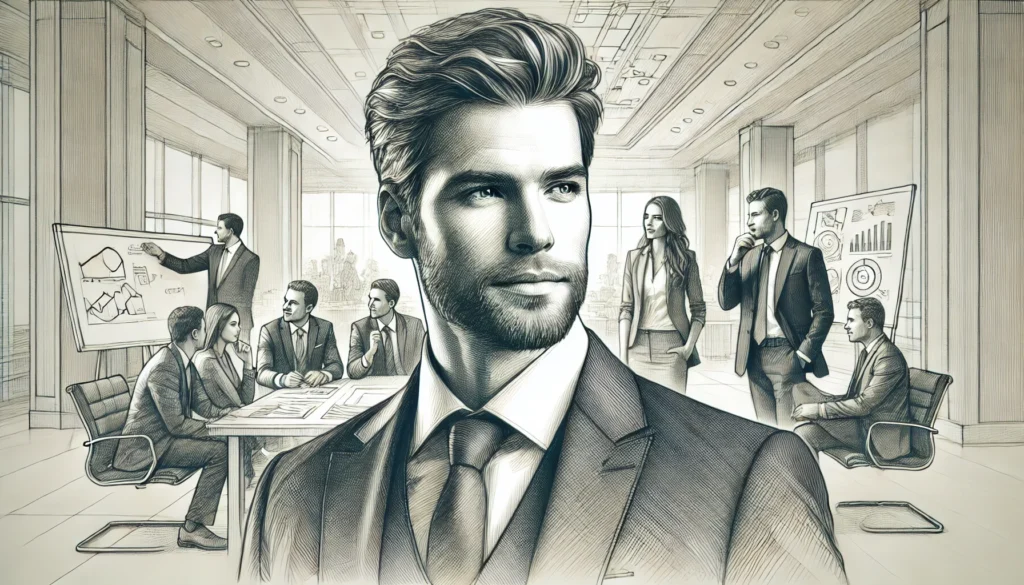
今回は、そんな私がこれまで実践してきたチームマネジメントの考え方、
そしてなぜ「リーダーに向いていない」と思っていた自分が、今もリーダーを続けているのか——
私なりの答えを綴っていきたいと思います。
リーダーに向いていないと思っていた私が、それでもマネジメントを続ける理由
私は、人前にしゃしゃり出て、自分をアピールするほうではない・・。
どちらかというと、周囲の状況を見て、追随し行動することが多いです。
外交的な性格でもなく、コミュニケーションもごく関係する一部の人で完結していました。
そんな私でも、リーダーとしてチームを導いていきたいと強く思ったのは、ある理由があります。
それは、チームの力を結集してシナジーを生み出し、最大限の成果を生み出すマネジメントに魅力を感じたからです。
関連する書籍の影響も大きかったように思います。
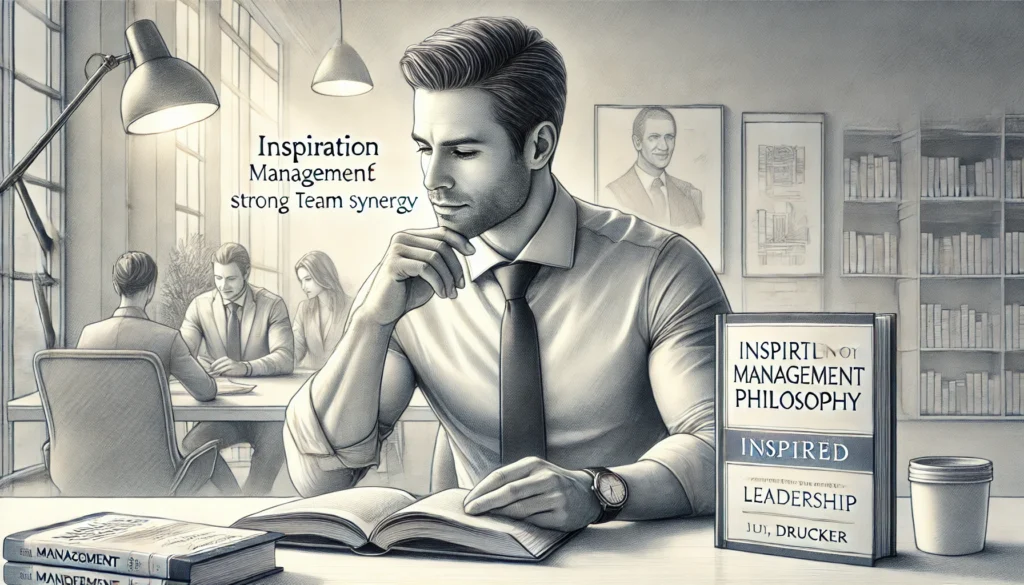
特にドラッカーのマネジメントに関する示唆は、大きく心を強く揺さぶられました。
私は子どものころから、チームスポーツに長年携わってきました。
チームワークの楽しさや喜び、一致団結した時のチームの強さなど、身をもって体験してきました。
そして社会人となり、マネジメント理論を知るにあたり、リーダーやマネジメントの在り方に、非常に魅力や可能性を感じました。
年齢とともに経験値が増えていくにつれて、より強く思うようになった次第です。
傾聴こそ、チームの可能性を引き出す第一歩
現在は「課長」として、組織の中で役割を担っています。
先ほども述べましたが、自分はリーダー性やカリスマ性は持ち合わせておりません。
どちらかというと「内向的」で「おとなしい」といった性質をもった人物です。
そんな私が、チームマネジメントにおいてできることの一つに「傾聴」があります。
「傾聴」は、チームの構成員とのやりとりの中で、「全身全霊、誠意をもって耳を傾ける」実際の行動をさします。
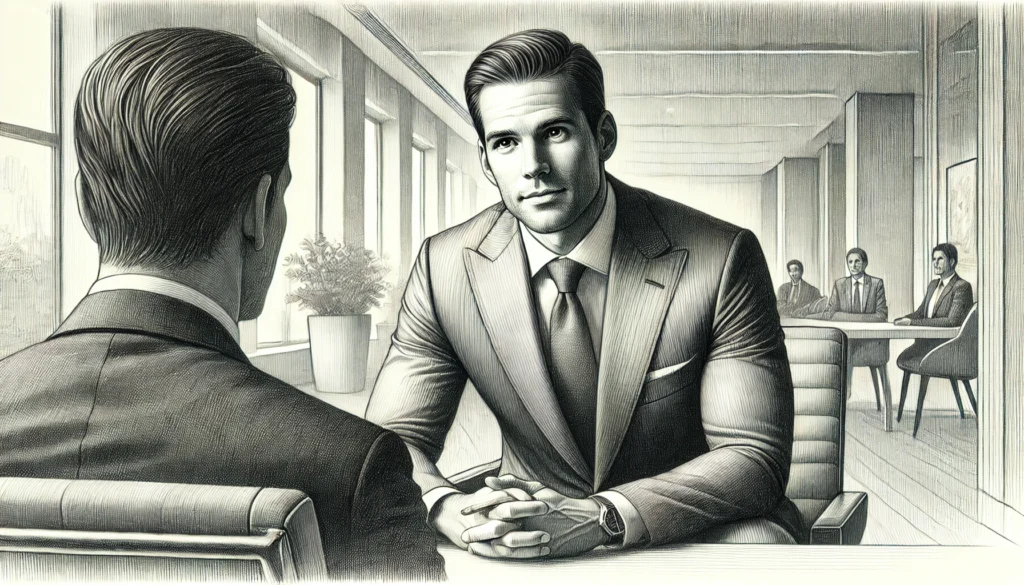
話を聴く際には、「おへそを相手に向ける」「やや前かがみになって聴く」「時々、質問したり相槌をうったりする」などを心構えとして持っており、かつ実践しています。
「相手は何を伝えたいのか」
「それはどのような背景があるのか」
「話し手の心情はどうか」
「課題点はあるか」
「現実可能なことなのか」
「それを近くで聴いている構成員の様子」
などを把握し、自分なりに思考をはたらかせながら聴いています。
そうすることで相手の意向、課題点などが見えてきます。
そして、それらがとてつもないチャンスにつなががる場合もあります。
やりとりの中で出された何気ない会話が、ある業務の時間効率化につながった例もありました。
傾聴で得た(最初は小さな小さな木くず)ともしびに、丁寧に風を送り(新鮮な空気を送り)周囲の人(まきに火をつけていく)と一緒に共有していくわけです。
そうすると、とてつもなく大きな成果につながることがあります。
「傾聴」は力です。
チームを俯瞰し、タスクを最適化する
傾聴で得た情報は、いったん預かることが多いです。
実際に現実的で実現可能か、メリットやデメリットは何か、どんな人材が必要か、計画スケジュールなどなどを構想します。
箇条書きにして、必要なタスクを書き出すと分かりやすいです。
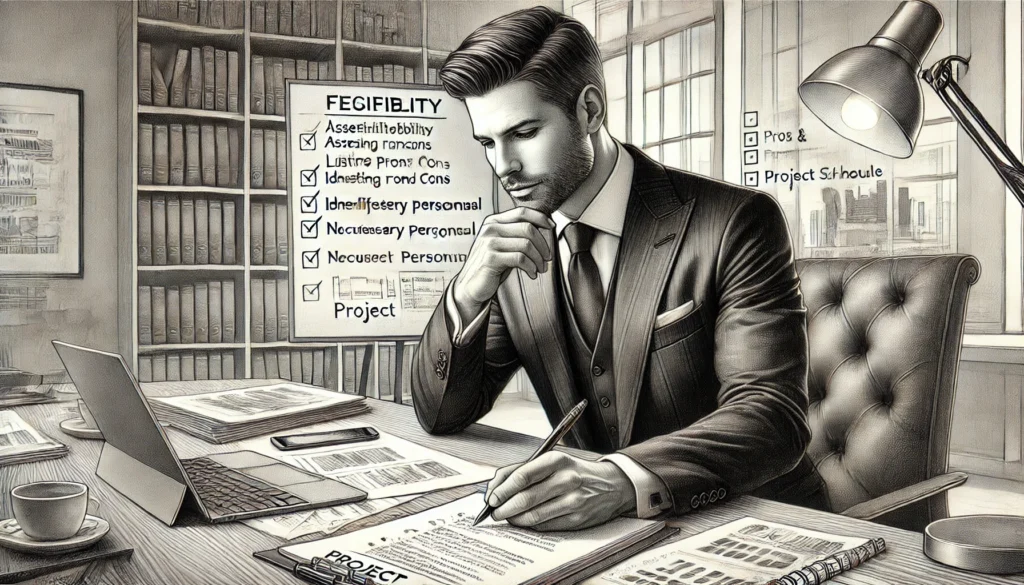
どんなスケジュールで運営していくのか、ゴールはどこかなどを踏まえ、まずはごく関係する小数人で情報を共有します。
主体者は、あなた(チームマネジメントを司る)です。
現状と比較して効率的な点はどこか、メリットやデメリットは何か、意見交換および情報共有をしましょう。
まず少人数で意見交換を行うと、構想を明確にすることができます。
その後、速やかにチームの構成員と情報を共有し、より精度を高めていきましょう。
構想が具体的になったら、構成員の過負担のならないように、タスクの明確化および分担をします。
その際、構成員の強みを生かすように役割を分担します。
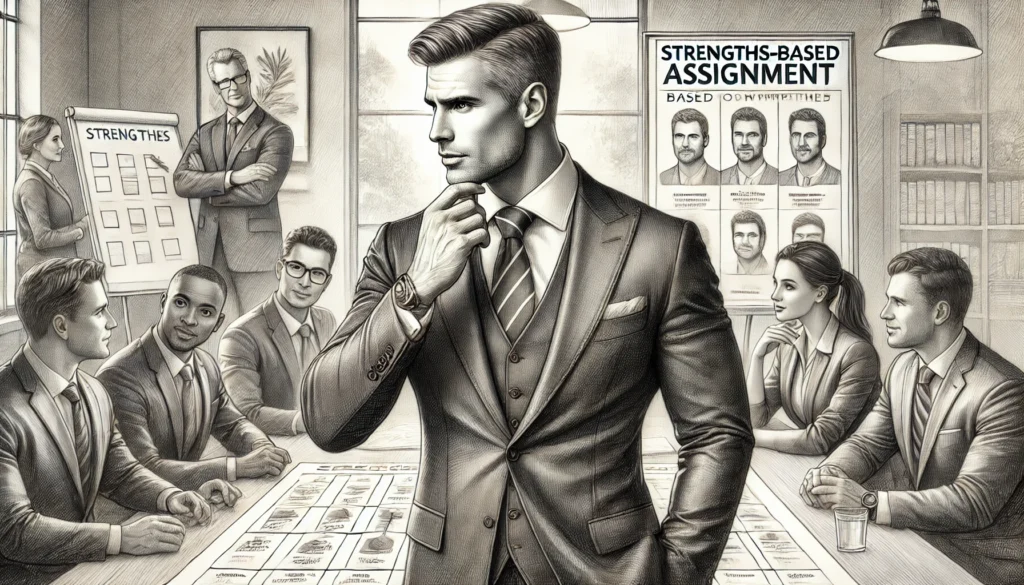
弱みを生かそうとしても、効果は薄く時間の無駄となります。
個々の強みをとことん伸ばすように、役割を分担する。
チームマネジメントの主体者であるあなたが、取りまとめましょう。
チームは関係性で動く——コミュニケーションの力
チームの構成員と、積極的にコミュニケーションを取りましょう。
そういう自分は、雑談が得意なほうではありません。
雑談は、対人関係における潤滑油になるといわれますが、無理にしなくてもいいと思います。
私の場合、自分の弱みで勝負しても(長期的にみて)あまり役立たないことを経験的に知っています。
ただし仕事に関する内容のことなら、すらすらとやりとりができます。
チームマネジメントの主体者は、コミュニケーションを通して仕事を練り上げていき、それらをとりまとめる力が求められます。
構成員と随時情報共有し、方針やタスクの内容を調整しつつ、プロジェクトをとりまりまとめていくイメージです。
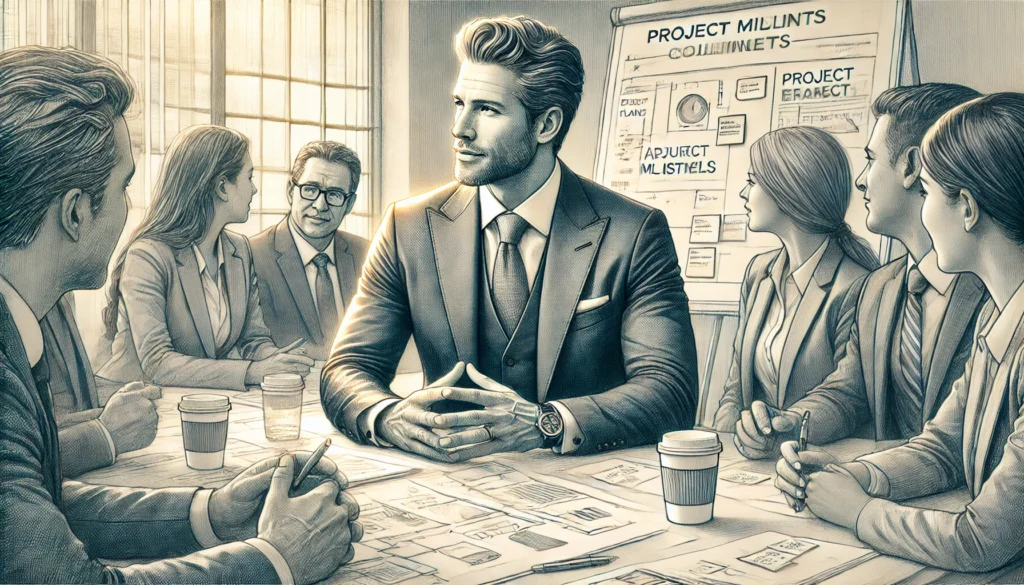
構成員とのコミュニケーションは欠かせません。
一人で考え、独断で決めようとすると・・・。
ろくなことが起こりません。
誰もフォローしてくれません。
成果が多少出たとしても、中長期的に継続することは難しいでしょう。
盤石にしたいのであれば、事前に構成員と積極的にコミュニケーションをとりましょう。
仲間とともに課題や情報を共有していくことで、難解な壁を超えることができます。
チームの力を侮ってはいけません。
一人でできることは、たかが知れています。
仲間と共に、強力な力を生み出しましょう!
率先垂範する——リーダーの覚悟
チームマメネジメントの主体者(リーダー)は、率先垂範が求められます。
自分が唯一できると確信するのは、率先垂範です。
なぜならば、自分のちょっとした勇気と努力次第で何とでもなるからです。
行動すべきと確信(判断)したら、誰よりもはやく率先して動きましょう。
先頭になって範を示すのです。
模範になるかどうかは分かりませんが、勇気をもって先頭を行くイメージです。
失敗してもめげません。
それは検証の一つの過程に過ぎません。
仮説と結果が一致しなかっただけです。
考察して、また新たな仮説を導き出せばよい。
そんな勇気を持ったリーダーの姿勢を、チームの構成員に示すこと。
チームが活性化します。
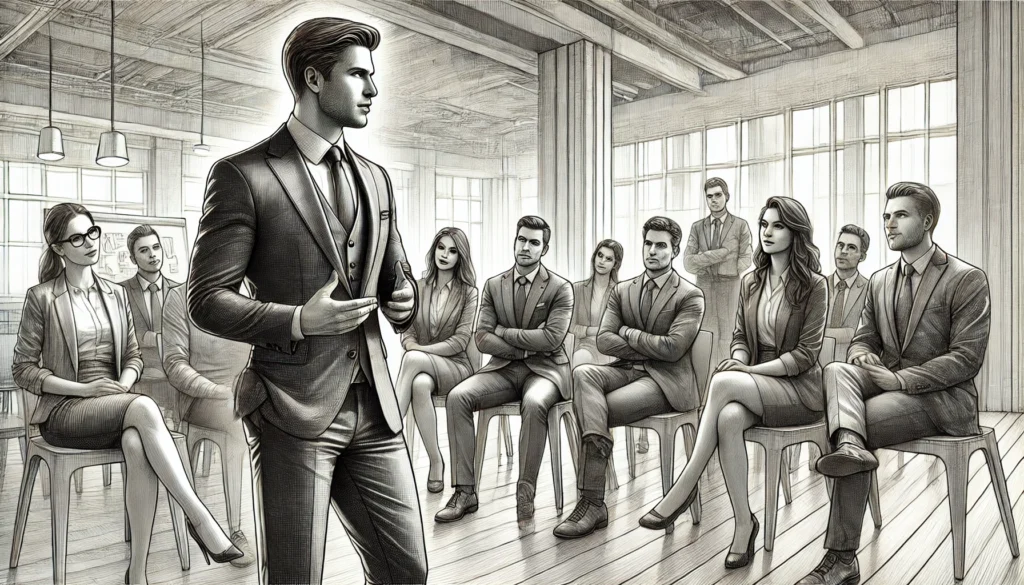
みんなに勇気を与えることができます。
それらは、チームのシナジーを生み出す強力な推進力となります。
まとめ
〇傾聴
〇俯瞰しタスクを最適化
〇コミュニケーション
〇率先垂範
一人でできる成果は、たかが知れています。
チームの力を結集して、大きなシナジーを出しましょう。
あなたには、どんな強みがありますか。
あなたの強みをどう生かしますか。
チームの力を信じて、勇気をもって行動しましょう。
失敗したら、それはラッキーです。
一つの仮説が、結果と一致しなかったことを証明できたのですから。
より精度の高い仮説を立てて、また検証していきましょう。
その過程で、あなたはより社会(組織や他者)に貢献できるリーダーになることができるのですから!!
一緒にがんばりましょう!
それでは、また!
結城一郎